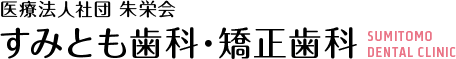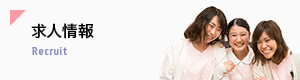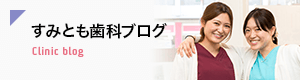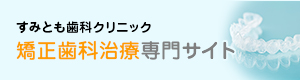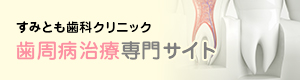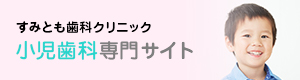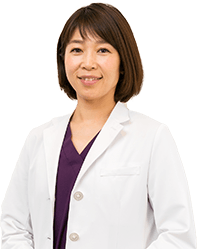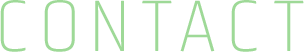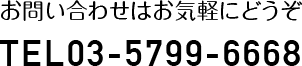ITI Section Japan Annual Meeting 2025に参加しました
2025年11月14日 (金)
カテゴリー : 未分類
みなさんこんにちは。東京都世田谷区にあり、東急世田谷線「上町駅」から徒歩1分のところにある歯医者、すみとも歯科クリニックです。
ITI Section Japan Annual Meeting 2025
日時:2025年11月9日
会場:東京コンファレンスセンター品川

ITI(International Team for Implantology)とは
世界中のインプラント歯科と組織再生医療の専門家が所属する、非営利の国際学術組織です。インプラント ITI 歯科の考え方は、「エビデンスに基づいたインプラント治療」と「世界規模の教育・ネットワーク」を軸に築かれています。
先日、当院の歯科医師・歯科衛生士で「ITI Section Japan/ITI Section Meeting」という、インプラント治療とインプラント周囲疾患(インプラントのまわりに起こる歯周病のような病気)についての講演会に参加してきました。今回は、その学びを患者様にお伝えさせていただきます。
講演ではまず、「健康なインプラント周囲の状態」と「インプラント周囲粘膜炎」「インプラント周囲炎」の違いを、写真や症例を通して詳しく復習しました。インプラントも天然の歯と同じように炎症を起こし、進行すると骨が溶けてしまうこと、そして“早く見つけて、早く対処すること”がとても大切だということをあらためて実感しました。診療の中でも、「インプラントも歯周病になる」という事実をご存じない患者様はまだ多くいらっしゃいますので、今後はリスクを事前にていねいにお伝えしていく必要性を強く感じました。
また、インプラント周囲炎の原因となるリスク因子についても、
・お口の中の細菌(プラーク)
・生活習慣や環境(喫煙・清掃状態・糖尿病など)
・その人自身の体質や持病
がどのように重なり合って症状を悪化させるのか、整理して学ぶことができました。特に、喫煙者は非喫煙者と比べて歯周病の発症が2~9倍多いこと、2型糖尿病の方はリスクが1.4倍高くなることなど、具体的な数字を教えていただき、今後の説明に活かせる内容でした。
さらに、インプラントならではのリスクとして、
・インプラントを埋める位置のわずかなズレが「磨きにくさ」に直結すること
・被せ物の形が汚れのたまりやすさに影響すること
・残ったセメントがじわじわと炎症を起こすこと
なども、実際の症例写真を見ながら理解を深めました。私たちが治療計画やメインテナンスを行ううえで、こうした点をしっかり意識し続けることの重要性を、あらためて感じています。
講演の中では、「人は目から入る情報をいちばん理解しやすい」というお話も印象的でした。いわゆるメラビアンの法則とよばれる考え方で、言葉だけでなく、表情や視覚情報が伝わり方を左右すると言われています。他院では、患者さんの歯みがきの様子を動画で撮影し、一緒に再生しながら磨き残しを確認したり、歯間ブラシのサイズや使う場所を、上下の歯列を撮影した写真に色分けして書き込んだりして説明している例が紹介されました。
当院でも口腔内カメラで撮影した画像を使ってご説明していますが、「一度聞いただけでは歯間ブラシの場所を忘れてしまう」というお声をいただくこともあります。今回の講演をきっかけに、
・歯みがきや歯間ブラシの使い方を動画で残してお見せすること
・写真に色分けして“ここにはこのサイズ”と視覚的に示すこと
など、よりわかりやすい方法を取り入れていきたいと考えています。
また、他院で実際に使われているインプラント周囲のメインテナンス用セルフケアグッズも多数紹介されました。当院でもスタッフ同士で使い心地を試し、患者様にも実際に使っていただきながら、「本当に良い」と感じたものを積極的に採用していく予定です。当院には、細菌レベルまでチェックしながらメインテナンスできる体制があり、これは大きな強みだと再認識しました。その強みをより活かすためにも、リスク因子の説明や禁煙・生活習慣のアドバイスにも、これまで以上に力を入れていきます。
講演を通して、スタッフ一人ひとりが「自分の説明は早口になっていないか」「患者様に本当に伝わっているか」を振り返るきっかけにもなりました。インプラントは「入れて終わり」ではなく、その後のメインテナンスと毎日のセルフケアが何より大切です。今回の学びを日々の診療に落とし込みながら、これからも皆さまのインプラントとお口全体の健康を、長く安心して守っていけるよう努めてまいります。
学会の後は皆で楽しく食事会に行きました。学会と食事会ともにとても充実した一日を過ごせました。